ピエール・ボナールは、19世紀末から20世紀前半にかけて活動したフランス人画家です。戸外や室内で日常的に目にする光景を豊かな色彩で描き続けました。ここでご紹介している作品から受ける穏やかさからすると、上に掲げた言葉は少し意外に響くかもしれません。ボナールは一体、絵の中でどういった「嘘」を重ね、それによってどのような「真実」をつくり出そうとしていたのでしょうか。

《ヴェルノン付近の風景》は、ボナールがフランス北部ノルマンディー地方に居の一つを構えていた時期に、自宅の近くで見た風景を描いた作品です。画面中央に見られるのはセーヌ河。クロード・モネが晩年を送ったジヴェルニーとはわずか5kmほどしか離れておらず、この作品の制作される3年ほど前にモネが没するまで、ボナールは親しく交友していました。制作中の睡蓮の大壁画を目にするなど、モネの制作に直に接したことの影響は、たとえば画面下部の花を描いた色彩の輝きに認められるかもしれません。
しかしボナールの風景画を特にユニークなものにしているのは、その画面構成でしょう。《ヴェルノン付近の風景》でまず注意が向かうのは、画面左、目の前に飛び込んでくるように大きく描かれた木の梢で、モネと同様に愛好していた日本の浮世絵の手法を思わせます。そればかりか、画面の四辺のほとんどが花や別の木の梢などで覆い尽くされ、通常、意識される視覚とは異なった眺めがつくり出されています。その結果、画面の半ばやや上を横切るはずの地平線が一部隠れていますが、これは作者があえて凝らした工夫にほかなりません。その工夫を可能にすべく、モティーフの配置をめぐる「嘘」がいくつも重ねられているというわけです。
これらの「嘘」に導かれるように、私たちの視線は明確な一点に収斂(しゅうれん)することなく、彩られた矩形の内部を隅々までさまようことを余儀なくされます。そのとき、河岸の風景は平面的な、あたかも一枚の色彩の織物のように立ち現れてはこないでしょうか。こうして画面の全体を通じて実現された豊かな絵画的効果こそが、ボナールが絵画において常につくり出そうとした「真実」であったのです。
「要は、生きた対象を描くのではなく、絵画を生きたものにするということである。」とは、ボナールの別の言葉ですが、20世紀にあって、あくまで自らの知覚と地続きにそれを行ない続けたところに、ボナールの偉大さがあります。またそこにこそ、絵画を描く理由があったのでしょう。
学芸員:島本英明




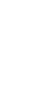
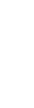
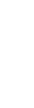
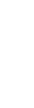
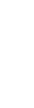
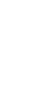
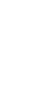
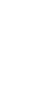
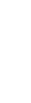
絵画にまったくふさわしい公式がある。一個の大きな真実をつくり出すためのたくさんの小さな嘘。
1945年の言葉